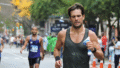こんにちは!
今日は「子どもへの算数の先取り学習」というテーマで書きたいと思います。
算数の先取りはどこまでやらせるべきか。「やった方がいい!」という声もあれば、「無理させすぎは逆効果」という意見もあって、親としては揺れます。
うちでも例に漏れず、先取り学習について悩んだことがありました。
でも今は、「やってよかった」と感じています。
それは、正しく“うちの子に合う形”でやれたからだと思っています。
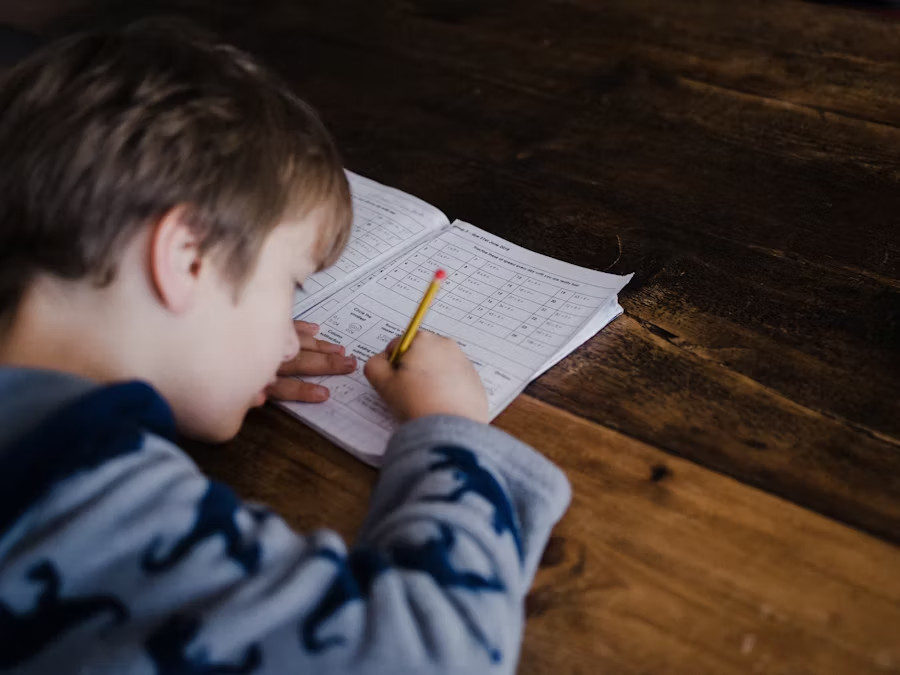
よく聞くアドバイス「子どもに無理な先取りはNGです」
まず、よくあるアドバイスとして、
「無理に先取りをしても意味がない」
「今の学年の内容をしっかり理解するのが大切」
この考え方、たしかに一理あります。
というか、すごくまっとうです。
子どもの理解力や興味関心を無視して、親だけが焦って先走ると、学習そのものが嫌いになることだってある。
それは本当に避けたいです。
でも、じゃあ「うちはまだ早いから…」と何もやらないのがいいのかというと、それもちょっと違う気がして。
そのあたり、けっこうもやもやしていた時期がありました。
「ちょっと背伸び」くらいが、うちにはちょうどよかった
そんな中で試してみたのが、チャレンジ(ベネッセ)の1学年上コースでした。
これ、やってみて思ったんですが、「すごくちょうどよかった」です。
理由は、学校の授業“復習”になるから。
予習っていうと難しく聞こえるけど、
チャレンジの教材ってイラストも多くて説明もやさしいので、子どもも「ちょっと先の内容」を気負わず読めるんですよね。
授業で先生の話を聞いたときに、「あ、それ知ってる!」ってなると、理解のスピードが全然違います。
まさに、「学ぶことのハードルが下がった」感じでした。
公文よりチャレンジがうちには合っていた理由
ここで少し比較の話をすると、公文式も試したことがあります。
確かに、反復練習の量はものすごいです。
計算が速くなるとか、学習習慣がつくとか、メリットはいっぱいある。
ただ、うちの子にはちょっと合いませんでした。
「またこれ?」「なんでこんなに同じ問題ばっかり?」とモチベーションが続かない。
一方、チャレンジは毎月届く教材に変化があって、ちょっとした読み物や実験ページがあるのも魅力。
「今日はこっちからやろうかな」って、自分で選べるのがよかったみたいです。
算数センスを磨く頭を使った問題集
次に試したのが、コナンの『12歳までに算数センスを育てる本』。
このタイトル、ちょっと煽り気味ですよね(笑)でも、やってみると内容は実に良質でした。
この本は、計算よりも「数の感覚」や「量のイメージ」を育てるものです。
単に問題を解くだけじゃなくて、「どっちが多い?」「どうやったら早く数えられる?」みたいな問いかけが多い。
こういうのって、日常生活で言葉にしにくい力なんですよね。
でも確実に、算数の土台になっていると感じました。
「マンガ×学習」の破壊力はすごかった
あと、個人的におすすめしたいのが、「10歳までに読みたい学習マンガ」系の本。
歴史・算数・理科など、いろんなジャンルがあって、しかもマンガだからハードルが低い。
「勉強ってこんなに楽しいんだ」って思わせてくれるきっかけになりました。
読書感覚でどんどんページをめくるうちに、気づけば知識が増えている。
これって、子どもにとってかなり理想的な学び方だと思います。
挑戦したのは、あの「ジュニア算数オリンピック」
ちょっと背伸びしてチャレンジしたのが、「ジュニア算数オリンピック」。
ええ、正直なところ、めちゃくちゃ難しいです(笑)
でも、問題がパズルみたいになっていて、本人はゲーム感覚で楽しんでいました。
練習には『明日への算数』という教材を使いましたが、これもまた骨が折れるレベルでハード。
ただ、それだけに「1問解けたときの達成感」は格別だったようです。
「もっとやってみたい」という気持ちが芽生えたのも、この時期でした。
「早すぎたらどうしよう」の不安もあった。でも…
ここまで書いてきて、「いやいや、そんなにいろいろやらせるなんて、大変でしょ」と思われたかもしれません。
その通りです。たしかに手間も時間もかかります。
「早くやらせすぎて、息切れしない?」という不安も常にありました。
でも、先取りって何かを詰め込むというより、「世界を広げてあげる」ことなんだなと今は思います。
知識が少し先にあると、興味を持つ範囲がグッと広がる。
そして、その興味が次の学びにつながっていく。
というわけで:先取り学習、うちはやってよかったです
「先取り学習ってやるべき?」という問いに、私の答えはこうです。
子どもの“今”を大切にしながら、ちょっとだけ未来を先に見せてあげる。
そのくらいの気持ちでやるなら、きっと意味があると思います。
全部の家庭に当てはまるわけではないですし、無理は禁物です。
でも、うちにとっては、子どもの「知りたい」を引き出す良いきっかけになりました。
もし今、何をやろうか迷っている方がいれば、ぜひ気軽にチャレンジしてみてください。
最初の一歩は、小さくて大丈夫です。